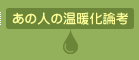本文の先頭です。
日刊 温暖化新聞|あの人の温暖化論考
私たちの豊かさの真の源は、自然である。社会の運営方法や人間のほかの生き物への態度を変えたいなら、「問題」と「症状」を区別しなくてはならない。
たとえば、今は誰もが温暖化について語っている。しかし温暖化は「問題」ではない。温暖化は問題の「症状」なのだ。私たちは、症状への対処にとどまらず、より深く考える必要がある。
ニコラス・スターン卿が書いた気候変動に関する600ページの報告書でも、問題の根本的な理由にまでは切り込んでいない。問題の根本とは、私たちが「精神」について考えるのをやめ、物質だけに注意を集中してきたことなのだ。いってみれば“物質主義”宗教に取りつかれてしまったのだ。しかし、物質は精神がない限り意味はない。人の体だって、それに命をもたらす精神がなくては、何の役にも立たないのである。
この200~300年の間、デカルトやニュートンといった多くの西洋の哲学者や科学者が、人間が支配する対象として地球を見てきた。私たちは、「人類とはまれな種であり、優れた種として地球を任されている」と信じるようになっている。
私たちは、かつて奴隷を所有していたように、いまでは自然を所有しているのだ。自然には権利はなく、私たちはいつでもどこでも、自然のものを自分の所有物だと言うことができる。しかし、私たちが違う世界観を持ち、自然を死んだものではなく、生きているものとして見た瞬間、突然、私たちは自然界と深い関係になることができる。そして、自然の権利は、私たち人間の権利と平等であることを認識するのだ。
実際には、人間も自然の一部なのだ。私たちは自然の一部であって、自然の所有者ではない。私たちは木や土地、川を所有しているのではなく、それらと関係を持っているのである。
現代に蔓延している「人間が自然を所有しており、従って、好きなように自然を取り扱ってよい」という考えは、根本的に間違っている。私たちがこの考え方を変え、「自然を所有することから、自然と関係を持つということへ」根本的にシフトできない限り、温暖化は止まらない。
化石燃料ではなく、風力、太陽光、原子力、バイオ燃料などで発電したとしても、それは症状の対処にすぎない。人間は自然から切り離された存在で、自然を所有していると考え、川や動物、熱帯雨林をコントロールできると思っている限り、持続可能性へ向けての私たちの努力はすべて、幻想にすぎない。技術的な解決は、心の変化によってバランスを取らねばならないのだ。
「所有」と「関係」は大きく違う。かつて「男性は女性を所有できる」と考えられていた時代もあった。何とか私たちはその考え方を変え、いまでは誰も自分の妻を所有することはできないことを知っている。そこにあるのは「所有」ではなく「関係」なのだ。
人々が奴隷を所有し、奴隷の数で富を測っていた時代もあった。しかし、森林や土地、動物たちは私たちの奴隷であるという考え方は今なお残っている。この人間中心のものの見方が続く限り、温暖化はなくならないだろう。
人間中心の世界観から地球中心の世界観に、大きく飛躍しなくてはならない。あらゆる命そのものが持つ価値を受け入れる必要がある。人間社会は、地球社会の一部なのだ。経済は、生態系と調和をした形で運営されなくてはならない。この世界観の変化と心の変化は、草の根から出てこなくてはならない。エコロジーの世紀をつくるために、“人々の運動”をつくり出す必要がある。
「政府が何かすべきだ」という幻想を持つこともできよう。しかし現実は、人々が地球との関係を変えない限り、世界は決して温暖化から逃れることはできない。私たちは、地球の客人であり、地球の友人でなくてはならないのだ。
西洋世界では人々は流行に従うものだが、現在の流行は温暖化について語ることだ。1960年代の流行は、核戦争について語ることだった。私はバートランド・ラッセル氏(当時92歳)に会ったとき、こう言った。「ラッセル卿、あなたは私にいつもインスピレーションを与えてくれています。しかし、あなたの哲学に関してひとつ問題があります。それは、あなたの核戦争に関する考えが恐怖によって動かされていることです」。
同じことが、気候変動に関する人々の意識の高まりにも起こっている。それは、恐怖に駆られたものになっているのだ。消費者主義の生活や自分たちの物質的な所有物を失ったらどうしようという恐怖である。環境運動の多くを動かしてきたのは、恐怖なのだ。
私はラッセル氏に「平和とは生き方なのです。平和は核兵器の恐怖から出てくるものではありません」と指摘したが、持続可能性も生き方なのである。単に「自分がいま持っているものを守るために何かをする」ということではないのだ。私たちは、恐怖という思考態度から脱却しなくてはならない。私たちの環境主義は、命やコミュニティ、人々、地球、自然への愛にインスピレーションを得たものでなくてはならない。
温暖化のかけらもなかった2600年前に、ブッダは環境主義者だった。彼は天啓を求めて木の下に座り、「私たちは樹木への愛を持たねばならない」と語った。しかし、今日私たちは、木の下に座ったりはしない。「この木をどのようにお金に換えようか。どうやってこの木で家や家具をつくろうか」と考える。
ブッダにとって、その木は神聖なるものだった。それ自体の価値を持っていたのだ。しかし、西洋文明にとって、木は単なる物体にすぎない。精神性を重視した経済(スピリチュアル・エコノミー)が私たちに教えるのは、「恐怖を持たず、地球を祝福せよ」ということだ。だからこそ私たちは環境主義者なのである。温暖化が怖いからではなく、地球を愛しているから地球を救いたいのだ。
スピリチュアル・エコノミーでは、あらゆる生きとし生ける者の関係は微妙なバランスの一部を成している。ミミズだって神聖だ。土壌を耕してくれるミミズがいなければ、食糧だってできない。だからミミズに敬意を払わなくてはならない。私たちが地球に対してこのような畏敬の念を持ちさえすれば、私たちの経済システムはすべて、ごく自然に持続可能なものになるだろう。
温暖化についての際限のない話が真の問題から私たちの気をそらしてしまっている。世界の温暖化へのアプローチはことごとく症状への対処である。誰もが――特に政治家やビジネスリーダーたち――この時流に乗ろうとしている。彼らは、地球を愛することを学んだわけではなく、「温暖化は経済成長のための新しいビジネスチャンスを提供する」という考え方に夢中なのだ。「経済成長、経済成長、経済成長」という呪文の虜になっているのである。
私は自分の呪文を唱えたい――「私の愛する地球、私の祝福する地球、私の楽しむ地球」。地球の恵みを享受するためには、地球を大事にし、その世話をしなくてはならないのだ。
温暖化の有無にかかわらず、地球を大切にすることは私たちの第一の責任である。もちろん、経済の果たすべき場はある。しかし、それはその場に収めておくべきであり、牛耳ることを許してはいけない。
ecosとはギリシャ語で「家」を意味し、logosは「知識」、nomosは「運営」である。自分たちの地球のわが家を知らずして、どうやって運営しようというのだろう。つまり、エコロジーが先に来るのだ。経済はエコロジーの次に来るものだと理解すれば、温暖化はなくなるだろう。経済至上主義とグローバル化が温暖化をもたらしているのだ。
私たちは、「果てしのない経済成長」よりもよい何かを求める必要がある。経済成長がつくり出した何兆ドルものお金が戦争や兵器のために使われていることを私たちは知っている。限度を超えたお金は負担になりうるのだ。不幸をもたらし、貧困や搾取を生み出してしまう。
お金は本当の富ではない。地球こそ私たちの富の真の源なのだ。富や貧困という極端がない中道を理想として求めるべきである。なぜなら、豊かな人がいれば貧しい人がいるからだ。もし私たちが貧困を過去のものにしたいのであれば、富も過去のものにしなくてはならない。バランスと公平さ、そして平静の状態がスピリチュアル・エコノミーなのである。
(2008年7月9日)
![]()
サティシュ・クマール
雑誌『リサージェンス』編集長、シューマッハー・カレッジ プログラムディレクター
1936年インド生まれ。9歳で出家しジャイナ教の修行僧となる。18歳のとき還俗し、農地改革運動に従事。ガンジーが目指したインド再生と世界平和の実現に取り組む。1973年から英国に定住。インドから米国まで約12,900キロの平和巡礼を、50歳で英国内の聖地を巡る約3,200キロの巡礼を、それぞれ一切の金を持たずに行う。英国南西部にスモール・スクール(中学・高校)とシューマッハー・カレッジ(持続可能で豊かな社会を創るための国際的な教育機関)を創設。2000年英プリマス大学教育学名誉博士号、2001年英ランカスター大学文学名誉博士号を授与される。主な著書に『君あり、故に我あり』『もう殺さない』ほか。世界を代表するエコロジー・平和・スピリチュアリティの思想家・活動家。