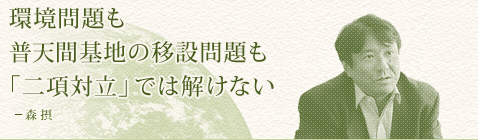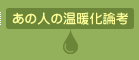本文の先頭です。
日刊 温暖化新聞|あの人の温暖化論考
雑誌「オルタナ」を創刊して3年経った。20年の新聞記者生活の後、独立して自分のメディアを持ったのだが、正直言って試行錯誤の連続だった。しかし、日本唯一の「環境とCSRのビジネス情報誌」の編集者として、実に多くの貴重な経験をさせて頂いた。3年という短い期間ではあるが、それを振り返ることで、後進のジャーナリストたちにも参考になるようなことを書き連ねてみたい。
オルタナがどんな雑誌かを理解して頂くには、これまでの主な特集記事を並べてみるのが一番だろう。
横並びCSRならやめちまえ/プロボノを知っていますか/良いバイオマス 悪いバイオマス/社会企業家 ヒト・モノ・金のつくり方/環境税は怖くない/環境・CSR経営 世界ベスト77社/ソーシャルなお金の貸し方/水素社会は島から始まる/ポスト・ブッシュ、環境大国へ/私が考える農業/バックキャスト経営を考える/温室効果ガス 目標巡り「明暗」/グリーン革命が始まった/シャンプーで世界を変える!/私が考える農業/社内をグリーンにする7つの方法/ソーシャルとブランドを考える/コンビニ24時間営業の是非/間違いだらけのエコカー選び/頑張れ!自然エネルギー/オーガニック1%の壁/ペットボトルの減らし方/不毛なゴミ論争 もう止めよう/自転車 危うい「ブーム」/森林ビジネス 今がチャンス/検証・カーボンオフセット
こうした特集記事を数多くつくってきた中で、環境問題の奥深さと、問題解決のためのプロセスづくりの大変さを多く学ばせて頂いた。
政治、経済、社会、事件・事故、文化、生活など、ジャーナリストにはあらゆる分野が取材対象として開かれているが、中でも環境分野は実にやりがいがある。
専門的な科学的知識が必要なだけではなく、生活と密着した感覚も問われる。政治家や役人へのアプローチだけでなく、NPO/NGO、企業、アカデミズムへの幅広い取材が求められる。
何より、答えが明らかになっていない問題が山ほどあり、今の科学技術のレベルでは解ききれないものも少なくない。
地球温暖化もその一つである。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次報告書には次のような記述があり、それが現在の地球温暖化に対する世界共通の認識となっている。
- 今後20年間の気温の上昇ペースは10年当たり約0.2℃と予想される。全ての温室効果ガスとエアロゾルが2000年当時の水準に保たれた場合は、10年あたり約0.1℃上昇すると推定される。
- 温室効果ガスが現状またはそれ以上のペースで排出され続けた場合、温暖化が進行し、地球の気候に多くの変化を引き起こし、その影響は20世紀中に観測されたものよりも大きくなる可能性がかなり高い。
- 人為的な温室効果ガスの増加が現在観測されている地球温暖化の殆どをもたらした可能性がかなり高いと結論づけられる。
しかし、それでも地球温暖化に対する懐疑論は根強く、世界のさまざまな専門家がこれに異議を唱えている。IPCCのメンバーの間で交わされたメール漏洩を端緒とした「クライメート・ゲート」というスキャンダルめいた騒動も起きた。
結局、真実はどこにあるのだろうか。
オルタナでは、もちろんIPCCの予測をベースにした紙面づくりをしてきた。しかし、この雑誌を3年やってきた中で「地球が温暖化しているか、そうでないかは、分からない」ことを前提にしたい――という皮膚感覚ができてきた。
人類はほんの400年ほど前、それまでの「天動説」とコペルニクスやジョルダーノ・ブルーノ、ガリレオ・ガリレイらによる「地動説」が拮抗していた。
ブルーノは、1600年に火刑に処された。ガリレオ・ガリレイも地動説を唱えたために迫害された。ローマ教皇庁はその後の1616年、地動説を禁じた。
わずか400年前、人類は「太陽が動いているのか、地球が動いているのか」、分からなかったのだ。それから科学は飛躍的に発達したとはいえ、未知の問題は数え切れない。その中で、これからの数百年、数千年にわたる地球の気候変動を断言し、対抗論者を非難する姿勢は、科学者としても一市民としても「謙虚な」姿勢と言えないのではないか。
私は科学の専門家ではないのでこれ以上のことは言えないが、「地球温暖化か否か」という「二項対立」の図式は、実は環境の分野では数多く存在し、これが正しい理解を妨げているケースが実に多い。下記の例を見てみよう。
(1) 原子力発電か、自然エネルギーか
化石燃料のピークアウトを控え、民主党政権も自然エネルギーの推進策を始めたが、それでも電力会社の関係者には「自然エネルギーは使えない」「石油代替は原子力しかない」という意見が大勢を占めている。
(2) 電気自動車(EV)か、ハイブリッド車か
オイルピークによりガソリン燃料が急騰すると、ガソリンは通常のモビリティの担い手としては使えなくなる恐れがある。では、ポスト・ガソリン車は何になるか。特にEVを推進する勢力は、すべての車両がEVに変わるという主張を強めている。果たしてそうだろうか。
(3) ペットボトルはリサイクルか、燃やすか
ペットボトルのリサイクルについては、燃やした方が環境負荷は少ないという説がある。
同様に、プラスチックの処理を巡っても、焼却か埋設かの議論も絶えない。最近ではプラスチックの分別停止や、焼却処分を選択する自治体が増えてきた。
ペットボトルやプラスチックなどのゴミ問題は、オルタナ6号(08年1月発売号)の「不毛なゴミ論争 もう止めよう」でも取り上げた。その中で、慶応大学経済学部の細田衛士教授(環境経済学)のコメントが明快であった。下記に引用する。
ゴミ問題では、埋めるか、焼くかという「0」「1」の議論をしても仕方がない。ゴミを埋め立てればメタンガスが出る。メタンガスは温暖化係数が高い。汚水の問題もあるし、何より、埋め立ての最終処分場が足りない。焼却、埋め立て、あるいはRPF(古紙や廃プラスチックを使った固形燃料)にする、など多様な方法の組み合わせで対処するほかないだろう。(中略)
循環型社会を実現するにあたって、ゴミを分別することは重要だ。歯磨きと同じで、習慣づけてほしい。今日できなかったのなら、明日やれば良い。ゴミの分別は、あれはダメとかこれが絶対良いとか言いにくい。無理のないやり方でやれば良い。自宅に庭があるのなら埋めるのが良い。生ゴミ処理機は電気を使うので良くない。
このコメントでよく分かるように、ゴミ問題は「0」か「1」かという、デジタル式の二項対立では決して解決しないことが分かる。ことは処理方法による環境負荷の多寡だけではない。地域の特性、住民感情、自治体の事情などさまざまな要因が複雑に絡み合っているのだ。
環境を巡る問題の多くは、このゴミ問題のように二項対立で語られることが多い。そして、もう少し視野を広げると、この「二項対立」の図式は日本の大手メディアで特に好んで取り上げられていることが実に多いことが分かる。例えば、
(4) 普天間基地の移設先は沖縄県外か否か
(5) 高速道路の値上げに賛成か反対か
(6) 外国人労働者を受け入れるか否か
――など、枚挙に暇がない。
いまメディアでは普天間基地の移設先にだけスポットが当てられているが、そもそも沖縄には36もの米軍施設が存在し、沖縄本島の面積の約18%を占めている状況こそ、メスが入れられなければならない。
高速道路も「1000円から2000円へ」という一律料金ばかりが注目され、高速道路の料金設定による車両通行量やそれによるCO2排出量への影響はメディアでは多く語られない。
環境問題も、普天間基地の問題も、ゴミ問題も「二項対立」ではなく、もっと「全体調和」が探られるべきである。
石油のピークアウトを克服するには、自然エネルギーだけでも、原子力だけでも解決しない。スウェーデンのカールグレーン環境相は、オルタナの取材に対して、2020年までに完全な脱化石燃料を目指していると語ったが、その内訳は、自然エネルギーと原子力発電の比率が半々であった。
日本のエネルギー政策についての筆者の見解は、原子力発電に一定部分は頼らなければならないものの、原発の新設には反対で、その分を自然エネルギーで補うべき、というものである。
モビリティについても、EVだけですべてをまかなうことはできない。現在7億台とされる世界の自動車のすべてをEVに変えることは不可能だ。それより、公共交通や鉄道をうまく組み合わせた次世代型の交通網に向けてのビジョン作りの方が大切だ。
そもそも、なぜ日本の、特にメディアで「二項対立」の考え方が多いのだろうか。
筆者の推論では、共通一次試験、その後の大学センター入試でのマークシート方式、選択回答方式が一つの背景にあるような気がする。選択回答方式は記述式よりデジタル思考になりがちで、思考のプロセスよりも結果を重視しがちである。
この推論が当たっているかは別としても、これからの環境問題は、こうした二項対立からできるだけ早く脱して、全体調和を探る形に移行することが、メディアにも行政にも一般市民にも求められている。
(2010年5月31日)
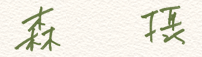
森 摂(もり せつ)
株式会社オルタナ代表取締役/雑誌「オルタナ」編集長
東京外国語大学スペイン語学科を卒業後、日本経済新聞社入社。流通経済部などを経て 1998年~2001年ロサンゼルス支局長。2002年9月退社。同年10月、ジャーナリストのネットワークであるNPO法人ユナイテッド・フィーチャー・プレス(ufp)を設立、代表に就任。 2006年9月、株式会社オルタナ設立に参画、編集長に就任、現在に至る。主な著書に『ブランドのDNA』(日経ビジネス、片平秀貴・元東京大学大学院教授と共著、2005年10月)など。訳書に、パタゴニア創業者イヴォン・シュイナードの経営論「社員をサーフィンに行かせよう」(東洋経済新報社、2007年3月)がある。