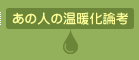本文の先頭です。
日刊 温暖化新聞|あの人の温暖化論考
第二次石油ショックが落ち着いた1990年代以降、日本人にとってエネルギーは水と同様、あって当然のものであり、その安定供給の必要性に注目が集まることもなかった。また、化石燃料価格が上昇傾向にある中でも、もっとも身近な電気の料金は、電源が多様化されていたこともあり、その上昇度合いは抑えられていた。安定供給も経済性についても満たされていたがために、東日本大震災までの10年ほどは、日本のエネルギー政策は温暖化対策に重きがおかれたものとなっていたと言ってよい。
しかし東日本大震災後、被災地にガソリンや灯油が届かなかったことや、東北・関東での計画停電などがあり、エネルギーというものは量的な安定供給が第一に重要であるということが多くの方に再認識されたのではないだろうか。また、震災からの復興にあたっては、生産活動のみならず、人々の生活という視点から見ても、エネルギーの価格上昇は大きな打撃となる。エネルギーは生活必需品であり、自家用車の利用が多い地方部、暖房需要の多い東北・北海道の人々の生活に、より重い負担となってのしかかってくるのだ。
もともと国のリソースが限られる中では、そうしたリソースを必要とする政策を立てるうえで、何を重視するかの優先順位をつけなければならない。現在の日本の状況を考慮すれば、エネルギー・環境政策に関しては、量的な安定供給、経済性、温暖化対策の順に優先順位をつけるべきである。そう考えると、2年前に鳩山元首相が掲げた温室効果ガスの1990年比25%削減という目標は見直されなければならない。この目標に対しては、当時から技術的にも経済的にもその妥当性について多くの疑問が呈されていた。しかし政府は、2030年に総発電電力量の半分以上をゼロエミッションの原子力とする「エネルギー基本計画」を2010年6月に策定し、何とか辻褄を合わせようとしたのである。
ところが、東日本大震災と原発事故により、この基本計画は「白紙」(菅直人前首相)からの見直しを迫られることになった。発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合を20%にしていくとの方針のようだが、同基本計画でも既に2030年にはほぼ20%を達成することが予定されていることを忘れてはならない。それを少しくらい前倒ししようと、2020年までに9基、2030年までに14基の新設追加を予定していた原子力による発電量を、再生可能エネルギーの導入だけで埋めることはとうてい不可能だ。省エネを最大限進めれば何とかなるとの見方もあろうが、実は同基本計画には現状に比べて一層省エネ努力をすることも前提として織り込まれており、これ以上の省エネを盛り込むのは非現実的である。
そうなると、原子力発電による予定供給分は、すべて化石燃料で代替するしかないのだが、そうなれば25%削減目標は絵に描いた餅以下となる。つまり、同基本計画や原子力発電の導入計画を見直すならば、温室効果ガスの削減目標も見直さなければならないということだ。25%削減目標は、鳩山元首相からトップダウンで提示されたものだが、今後の見直しにあたっては、国際的公平性、実現可能性、国民負担の妥当性という重要な観点を踏まえ、現実的な水準にすることが重要である。国際的公平性に関しては、どのような指標を用いるかが意見の分かれるところであるが、指標の在り方を含めて科学的かつ客観的に検討していくことになろう。また、実現可能性と国民負担については、実行できる対策をボトムアップで積み上げ、その削減量とかかるコストを試算した上で、地に足のついた検討を行うことが必要である。
一方、地球温暖化を巡る国際交渉は、依然として先行きが不透明な状況である。昨年のCOP16では日本政府自ら、米国が抜け中国などの途上国が削減義務を持たない京都議定書では温暖化問題は解決しないとの正論を述べ、そうした枠組みを固定化してしまう同議定書の第二約束期間にコミットしない立場を明確にした。途上国からの排出増加が急増する将来を考えれば、京都議定書の延長は地球温暖化問題の真の解決策とはならない。こうした日本の明確な意思表示もあり、目標設定がトップダウン的に行われる京都議定書に替わって、各国の自主的な取組みを基礎とするカンクン合意が実現した。
その中身としては、途上国に対する資金支援策(「緑の気候基金」設立)、技術協力メカニズム、森林保護(REDD)、温暖化進展への「適応」措置に関する支援など、途上国に対して新たな枠組みへの参画を促すためのインセンティブ措置の概要が含まれている。途上国が京都議定書にこだわる理由の一つが、同議定書の下でのCDM(クリーン開発メカニズム)などに代表される先進国からの資金・技術移転の仕組みの継続にあることを考えれば、この意味は大きく、新しい枠組みを構築する要素は揃ってきたと言える。しかし、今年のCOP17でも京都議定書延長とカンクン合意路線とのせめぎ合いは続くと見られており、新しい枠組みが構築されるかは予断を許さない。 こうした中、日本は下記のような内容の方針を、早く国際的に発信すべきである。
上述したように震災後の状況変化で難しくなった国内対策を主とする削減政策から、グローバルな対策で温室効果ガスを削減することにシフトすることである。今後の排出量の増分はほとんどが新興途上国からと予測されていることから、特に途上国の排出増加の抑制や削減に貢献していくことが有効である。日本は今、震災からの復興という優先課題に多大な国費を投入しなければならない状況である。限界費用が極端に高い国内での削減にこだわっていては、コストパフォーマンスが悪過ぎ、結局日本の貢献度が小さくなってしまう。
そのために、日本が有する世界トップの省エネ技術や高効率な火力発電技術などを活用することで、世界の温室効果ガス削減に貢献していく方針を世界に発信することが重要だ。日本の主要産業のエネルギー効率は世界最高水準を維持しており、日本のBAT(Best Available Technology)が世界に普及した場合、2020年時点で世界のCO2排出を約63億トン削減できるとの試算もある。このような日本の技術を使った製品やインフラの建設及び運用におけるノウハウを輸出していくことで、温暖化対策への貢献とともに国の成長にも寄与することができる。
ポスト京都の枠組みも、グローバルな視点で削減に取り組める枠組み、省エネ等の技術が生かされる枠組みを目指すべきである。具体的な枠組みの内容としては、カンクン合意に基づくボトムアップ型のプレッジ・アンド・レビュー方式(参加各国が自らの目標・行動計画を提出、誓約し、その取組み状況を国際的に評価、検証する仕組み)である。そして、途上国に技術移転を促進していく新たな制度として、現在政府で進めている二国間クレジットメカニズムを、CDMを補完・代替するものとして国際社会に提示していくことも求められる。さらに、その制度のインフラとして、各国の削減努力の透明性や実効性を確保するために必要となるMRV(測定・報告・検証)のルール確立にも、日本の知見を提供していくべきである。
このような具体的な提案を通じて、日本は、枠組みの空白期間よりも削減行動の空白期間を生じさせないことが重要だということを世界に発信しつつ、次期枠組みの構築に貢献していくことが期待される。
(2011年10月13日)
![]()
澤 昭裕(さわ あきひろ)
(特定非営利活動法人)国際環境経済研究所 所長
1957年大阪府生まれ。1981年一橋大学経済学部卒業、通商産業省入省。1987年行政学修士(プリンストン大学)。1997年工業技術院人事課長。2001年環境政策課長。2003年資源エネルギー庁資源燃料部政策課長。2004年8月~2008年7月東京大学先端科学技術研究センター教授。2007年5月より21世紀政策研究所研究主幹。
著書に『地球温暖化問題の再検証』東洋経済新報社(2004年)、『エコ亡国論』新潮新書(2010年)。21世紀政策研究所の提言書として『地球温暖化国際交渉に関する政策提言』(2009年)『地球温暖化問題の新たな政策課題』(2009年)など。