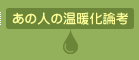本文の先頭です。
日刊 温暖化新聞|あの人の温暖化論考
石油文明の崩壊がもたらした世界同時不況
文明史的視点でいえば、今度の世界同時不況は、20世紀の豊かさを支えてきた石油文明の崩壊に伴う構造不況である。通常の循環型不況なら在庫調整が終われば、景気は数年もすればなにもしなくても自律回復してくる。しかし、構造不況は、不況をもたらした原因を究明し、それを取り除かなければ、不況からの回復は難しい。今度の不況は100年に一度あるかないかの典型的な構造不況の性格を備えていると言えるだろう。
その謎解きのためには、少し歴史を振り返らなければならない。
18世紀後半、イギリスで始まった産業革命は、瞬く間に欧州大陸、アメリカ、そして少し遅れて日本にも広がった。それまで人手に頼っていた仕事を機械に置き換えることで生産性が飛躍的に向上し、人類に未曾有の繁栄をもたらした。それを支えたのが化石燃料だった。産業革命期には蒸気機関が強力な動力源として登場し、石炭がそれを支えた。20世紀に入ると石油が主役に躍り出る。20世紀の産業を代表する自動車は全面的に石油に依存してきた。
イギリスの産業革命以降今日までの約250年間、世界の経済発展は「ハイカーボングロウス」(化石燃料依存型成長=HCG)に支えられてきた。しかし、ハイカーボングロウスは、環境破壊型、資源収奪型の成長だったため、地球の限界に突き当たり、地球温暖化現象など様々な弊害を引き起こし破綻してしまった。それが今度の不況の原因である。
これからは、「ローカーボングロース」(低炭素型成長=LCG)への転換が求められる。ローカーボングロースは、化石燃料の消費節約、削減を可能にさせる技術、投資、新規需要に支えられた持続的で安定した経済成長を可能にする新しいタイプの成長路線である。
デカップリング経済への転換を推進
LCGへ向け大きくカジを切るためには、環境保全、資源循環、省エネルギー、新エネルギー、省資源などの分野で、ブレークスルー(現状打破)を伴うイノベーション(技術革新)を引き起こさなければならない。さらにそれらの分野への積極的な設備投資、新規需要の開発・拡大を通して、新産業群を育て、これまでとは違った新しい経済成長を目指さなければならない。
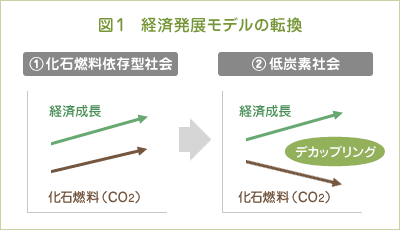
LCGへの転換を可能にさせるための政策がデカップリング政策である。デカップリング(decoupling)とは、密接な関係にある2つの要素を引き離すことである。何を引き離すのか。経済成長と化石燃料との密接な関係を引き離すのである。そのためには経済発展モデルの転換が必要だ(図1)。産業革命以降今日まで、経済成長と化石燃料との関係は、切っても切れない密接な関係にあった。経済成長のためには化石燃料を大量に使わなければならなかった。逆に言えば、化石燃料を大量に使うことができなければ、高い経済成長を実現させることが不可能だったのである。両者はいつも手を取り合い、同じ方向に向かって歩み続けてきた。それだけに、両者の関係を引き離すことなど考えられなかったし、「両者の関係を引き離せば、経済成長は止まってしまう」と信じて疑わない経済人が今でも多数派ではなだろうか。
そうした常識の世界に「両者を引き離さないと、今度の不況から脱出できない」という異質の考え方が登場してきたのであり、既存の産業界にとって青天の霹靂のような驚きを持って迎えられた。だが、「事実は小説よりも奇なり」である。21世紀に入った頃からあり得ないと考えられてきた両者の引き離しに成功する国が次々と登場してきたのである。化石燃料の消費、別の言い方をすれば、CO2の排出量を削減させながら、一方で右上がりの経済成長を実現する国が登場してきたのである。
EU諸国は成功、日米はいまだ未達成
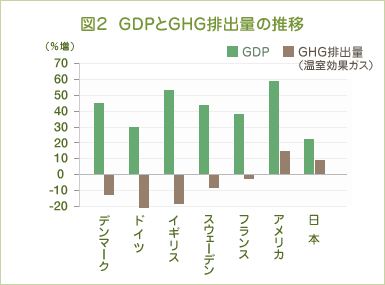
図2は1990年と07年の実質GDPと温室効果ガス(GHG)の変化を示している。GHGの大半はCO2で占められているので、GHG=CO2と考えていただいて差し支えない。図の見方は、90年を基準にして、07年までにGDPおよびGHGがどの程度増えたのか減ったのかを示している。たとえば、デンマークの場合、GDPは90年比で45%増加した。これに対しGHGは逆に13%減少したことが分かる。GHGの排出量を削減させながらGDPは増加している。デカップリングに成功したのである。ドイツ、イギリスも同様である。フランスは原子力発電への依存が大きく、化石燃料依存が相対的に低いため、京都議定書の削減約束は、90年比0%だった。スウェーデンの場合も、電力の大部分は原子力発電と水力発電で賄われており、石油など化石燃料への依存は、主として暖房や給湯、自動車などの輸送部門に限られており、化石燃料依存はそれほど高くない。そのため京都議定書では、削減どころか90年比4%増が認められている。
それにもかかわらず、フランスのGHG排出量は90年比2.7%減、スウェーデンは同8.7%の削減を実現している。
これに対し、日本やアメリカはどうか。まずアメリカだが、化石燃料依存型の従来通りのやり方を踏襲し、GDPは約60%増と主要国の中で最も高いが、同時にGHGの排出量も約15%増とずば抜けて多い。現在、経済発展の著しい中国やインドもアメリカ型で、GHGの排出量をどんどん増やしながら、GDPを拡大させている。
日本はどうか。GDPの増加率は22%で、主要国の中で最も低い。年率ベースでは1%増程度で低迷しているが、GHGの排出量は90年比8.7%増でかなり大きい。
化石燃料依存型では、日本の景気回復は無理
EU諸国がデカップリングに成功したのに対し、日米が依然、旧来型のカップリング状態に止まっているのはなぜだろうか。この点については、中長期的視点に立って、EU諸国が環境税の導入などデカップリング政策を計画的かつ着実に進めたのに対し、日米はデカップリングのための政策を実施してこなかった。その違いが、17年の歳月を経てはっきり現れてきたことが指摘できる。
一方、カップリング政策からいまだ抜け出せないでいる日本とアメリカとを比較するとここでも大きな違いがある。アメリカは京都議定書の約束である90年比7%削減の採択に署名した。しかし、01年1月に共和党のブッシュ大統領が就任すると、同年3月に京都議定書から離脱してしまった。
この結果、アメリカはGHGの排出削減の義務を負うことなく、これまで通りのやり方でCO2を大量に排出しながら高い成長を目指すことができた。
これに対し、日本は京都議定書が定めた90年比6%削減の義務を負っている。12年末までに目標を達成するために、CO2の排出量を厳しく規制しなければならない。日本の場合、温室効効果の約90%がCO2の排出によって引き起こされている。そのため省エネ法や地球温暖化対策法が毎年のように改正・強化され、企業のCO2排出削減コストはかさむ一方だ。いまやGHG削減対策は、企業経営にとって大きなコストアップ要因になっている。この傾向は今後一段と強まってくることが予想される。このため、日本が化石燃料依存型の経済発展にこだわり続ければ、CO2排出規制によって企業経営は一段と苦境に追い込まれるのは避けられない。
デカップリング経済へ3つの柱
日本がLCGを目指すためには、デカップリング政策の強力な推進が必要である。図3はデカップリング経済移行のための三つの柱である。第1が新エネルギーなどの技術開発、第2がそれを可能にさせるための新制度設計、第3が自然再生である。図にある環境保全型公共投資とは、歩道や自転車道の整備拡充、3面コンクリート張りの河川修復、電気、ガス、水道などのライフラインを共同管理する共同溝の建設などである。
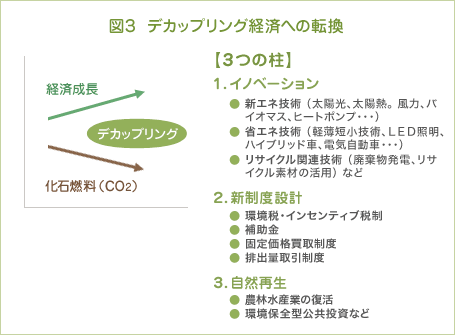
民主党政権は温暖化対策に対し積極的で温室効果ガス(GHG)の排出量を2020年に90年比25%削減、50年には同80%削減を掲げている。またこの目標を達成するために、地球温暖化対策基本法案の成立を目指している。残念なことに昨年春の通常国会では党内のごたごたで廃案、秋の臨時国会でも同様の理由で継続審議になってしまった。今年の通常国会での成立を期待したい。
同法案には、図3で示した新制度設計の重要な部分が盛り込まれている。同法案を早期に成立させ、ヒト、モノ、カネ、ジョウホウをこの分野に集中させることが、景気回復に最も効果的である。
90年代の不況に対し、政府は道路を中心とする公共投資に巨額の財政をつぎ込み、ゼロ金利政策の推進で不況を克服しようとしたが、財政赤字を膨らませただけで失敗に終わった。
冒頭で指摘したように、今回の不況は100年に一度あるかないかの構造不況であり、不況を乗り切るためには、経済成長と化石燃料の密接な関係を引き離さなければならない。
引き離すための政策がデカップリング政策であり、デカップリング政策の実施が新たな技術、投資、新規需要の創出を促すことになる。
このような視点からいえば、地球温暖化対策基本法は、実は緊急景気対策法と名付けた方が分かりやすいかもしれない。基本法案を早期に成立させ、実行に移すことが、最大のかつ最も効果的な景気対策になることを与党だけではなく、野党も認識すべきである。
(2011年1月25日)
![]()
三橋 規宏(みつはし ただひろ)
経済・環境ジャーナリスト/千葉商科大学名誉教授
1964年慶応義塾大学経済学部卒業、日本経済新聞社入社。ロンドン支局長、日経ビジネス編集長、論説副主幹などを経て、2000年4月千葉商科大学政策情報学部教授。2010年4月から同大学大学院客員教授。名誉教授。専門は環境経済学、環境経営論。主な著書に「ゼミナール日本経済入門24版」(日本経済新聞出版社)、「グリーン・リカバリー」(同)、「サステナビリティ経営」(講談社)、「環境再生と日本経済」(岩波新書)、「環境経済入門第3版」(日経文庫)など多数。中央環境審議会臨時委員、環境を考える経済人の会21(B-LIFE21)事務局長など兼任。